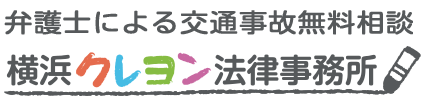著者情報
弁護士 鈴木 晶
一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
交通事故に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。

交通事故における後遺障害認定とは、事故による怪我や障害が治療を経ても完全には消えず、将来にわたって継続する障害の程度を公的に評価・認定する制度です。
この認定は被害者の将来の生活や補償に大きく関わる重要な制度であり、加害者側の任意保険会社を介して認定を求めることも可能ですが、「被害者請求」として被害者の方自身で直接請求をすることも可能です。
この被害者請求について当記事で深掘りし、この請求方法によることのメリットやデメリット、具体的なやり方なども解説していきます。
後遺障害等級認定手続きの概要

後遺障害の認定に向けては、まず医師による治療が一定期間行われ、「症状が固定した」と判断される必要があります。
そして、その時点での詳細な診断書や各種検査結果などの医療記録を揃える必要があります。これらの資料は、後遺障害の程度を客観的に示し、等級を決めるうえでの重要な証拠となるためです。
また、認定手続きにおいて特に注目すべき点は、被害者自身が直接認定についての請求ができる「被害者請求」という制度の存在です。
これは、被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請や保険金請求を直接行うことができるという内容になっています。
被害者請求を選択するメリット

被害者請求を選択することには、以下のような重要なメリットがあります。特徴をよく理解して手続きに取り組みましょう。
早期に賠償金が受け取れる
被害者請求の大きなメリットの1つが「示談成立前に賠償金の一部を受け取れること」です。
通常、交通事故の賠償金は示談成立後や裁判での和解・判決後に支払われますが、被害者請求を行うことで、より早い段階で自賠責保険からの支払いを受けることができるのです。
この利点は、特に以下のようなケースで大きな意味を持ちます。
- 事故による怪我で働けず収入が大幅に減少しているケース
例)日雇い労働者が交通事故で腰を痛めてしまい数ヶ月間働けなくなった場合、生活費の確保が急務となる。 - 高額な治療費が必要なケース
例)脊髄損傷で長期の入院と高度な手術が必要となった場合、医療費の負担が家計を大きく圧迫する。 - リハビリや介護サービスが必要なケース
例)脳挫傷により後遺症が残り、長期的なリハビリや介護が必要となった場合、これらのサービス利用費用の確保が重要。
公平な等級認定が期待できる
被害者請求を行うことで、後遺障害等級の認定においてより公平な結果を得られる可能性が高まります。このメリットは、以下のような点から説明することができます。
- 被害者が直接情報提供できるため
→ 被害者自身が詳細な資料を提出できるため、自身の症状や障害の状態をより的確に伝えることができる。例えば、日常生活における具体的な困難さや、仕事への影響などを詳細に記述することが可能。これにより、医学的な所見だけでは捉えきれない生活上の支障を適切に評価してもらえる可能性が高まる。 - 中立な判断が期待できるため
→ 任意保険会社を介さずに直接請求を行うため、保険金支払いを抑えたい保険会社の意向が反映されるリスクが低減され、利害関係に左右されないより中立的な判断が期待できる。 - 手続きの透明性が高いため
→ 被害者自身が直接手続きを行うことで、認定プロセスの透明性が高まる。どのような資料が考慮されたか、どのような基準で判断されたかなどの情報をより直接的に把握できる。
なお、被害者請求によらず申請をしたからといって加害者側の意向が強く反映されるわけではありません。いずれにしろ公的機関による公平な審査が入ります。
医学的根拠に基づく認定であることも同様です。認定にあたっては診断書や各種検査結果などの医学的根拠に基づいて判断が下されます。
任意保険非加入でも対応できる
加害者が任意保険に加入していない場合でも、被害者請求をすることで自賠責保険からの補償を受けることができます。
また、もし任意保険の会社が後遺障害認定になかなか対応してくれない場合でも、被害者請求という選択肢を持っておけばすぐに手続きを進めることができます。
納得感が得やすい
被害者側で手続きを進めるため、手間がかかる反面、納得感は得やすいです。
保険会社任せとならず自己管理することで主体的な判断が可能となり、認定申請においてどの症状をどのように申告するかを自ら決定できます。
複数回の請求が可能
被害者請求は、請求期限および限度額に達するまで何回でも行うことができます。
ただし、自賠責保険には支払限度額があるため(死亡:3,000万円、後遺障害:75万円~4,000万円、傷害:120万円)、この限度額を超えての請求はできません。
被害者請求を選択するデメリット

被害者請求には多くのメリットがありますが、同時にいくつかの重要なデメリットも存在しています。手続きに着手する前にこちらのデメリットについても確認しておいてください。
手続きの負担が大きい
被害者請求は、自ら直接手続きを行わなければいけませんので、必要書類の収集・作成に多くの時間と労力を費やすことになってしまいます。この点が代表的なデメリットです。
また、医療機関など関係機関とのやり取りに手間を感じることもあるでしょう。
専門知識が必要
保険や法律に対する知識が十分ではない場合、被害者の方だけで対応するのはリスクが大きいです。
ただしこの点については弁護士に相談・依頼することで解決が図れます。
無料相談はこちら
Tell:045-479-5928(受付(平日)9:30~22:00(土日祝)11:00~18:00 )
被害者請求のやり方

被害者請求によって後遺障害等級の認定を受けるようとするなら、以下の手順に沿って手続きを進めていく必要があります。
- 必要書類を準備
- 自賠責保険会社に書類を提出
- 損害保険料率算出機構による審査を受ける
- 審査結果の通知を受ける
- 賠償金を受け取る
各手順の詳細を以下に示します。
手順①必要書類を準備
被害者請求に必要な主な書類は次のとおりです。
- 請求書(自賠責保険会社所定の様式を使用)
- 後遺障害診断書(医師に作成してもらう)
- 交通事故証明書(警察署で発行してもらえる)
- 事故発生状況報告書(事故状況を詳しく記載した書類)
- 印鑑登録証明書(請求者本人であることを証明するために使われる。自治体の役所で発行請求できる。)
- 診療報酬明細書(治療を受けた医療機関から発行してもらう)
場合によってはレントゲン写真やMRI画像などの医学的資料をさらに用意することもあります。
手順②自賠責保険会社に書類を提出
準備書類に不備がないことを確認し、加害者側の自賠責保険会社に提出します。必須ではありませんが書類一式に加え連絡先等を記載した送付状を作成しておくと良いでしょう。
なお、通常書類は郵送で提出します。重要書類のため追跡もできるよう書留郵便で送付すると良いです。
手順③損害保険料率算出機構による審査を受ける
自賠責保険会社が被害者(加害者請求の場合は加害者側の任意保険会社)から提出された後遺障害認定の申請に関する書類を受け取ります。そして保険会社は受け取った書類を「損害保険料率算出機構」に送付します。
申請を受けた保険会社が直接審査して支払いを行うのではなく、一度第三者の立場にある損害保険料率算出機構がチェックするプロセスを挟むのです。
損害保険料率算出機構は、自賠責損害調査を通じて各種保険における保険料率の算出を行うなどの役割を担っている団体のことです。後遺障害等級認定においても同機構が関与し、調査を実施。等級認定の審査を行います。
手順④審査結果の通知を受ける
損害保険料率算出機構での調査・審査が終わると、その内容が自賠責保険会社に対し報告されます。
そしてこれを受けた保険会社がさらに申請を行った被害者に対し審査結果の通知を行います。
もし、通知された結果に納得がいかないのなら、異議の申立ても検討しましょう。認定結果に不服がある方が利用できる手続きも用意されていますので、再度相手方の自賠責保険会社に対して異議申立書を提出し、審査を求めることが可能です。
なお、異議申立てに関しては回数制限がなく、何度でも審査を求めることができる仕組みになっています。とはいえ追加資料を提出するなどしなければ結果を覆すことは難しいです。
そこで、より症状について詳細に記載した後遺障害診断書を用意したり、CT、MRI等の新たな画像資料を用意したり、あるいは専門医による意見書を用意するなどの対策が必要となるでしょう。
手順⑤保険金を受け取る
後遺障害等級の認定を受けた後は、自賠責保険会社から後遺障害に対する保険金が支払われます。指定の口座に振込が行われますので確認しましょう。
なお、申請から振込までの期間は通常1~3ヶ月程度といわれていますが、複雑な後遺障害の事案や異議申立てをしたケースなどではさらに時間がかかります。
後遺障害等級に基づいて損害賠償額を算定しよう
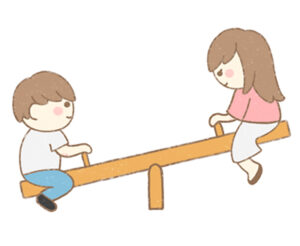
自賠責保険からの受け取れる金銭は、最低限の補償を目的としたものです。そのため保険金を受け取ってもそれだけで十分とはいえないケースが多いでしょう。
そこで実際に生じた損害額を算定し、不足分を加害者側に請求することとなります。このとき、上記の手続きにより認定を受けた後遺障害等級をもとに計算を進めます。
「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」の具体的な金額を算定しましょう。後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったことに対する身体的精神的苦痛を金額に置き換えた賠償金のこと。逸失利益は労働能力低下による将来の損失分を金額に置き換えた賠償金のことです。
ただし、算定した金額に相手方が応じるとは限りません。交渉が必要となりますし、場合によっては裁判所で解決を図ることになるかもしれません。保険会社とは経験値やノウハウにも大きな差があるため、被害者の方も弁護士にご依頼していただき、納得のいく支払いを目指しましょう。
横浜クレヨン法律事務所では年間150件以上の交通事故案件を取り扱い、年間相談件数は400件以上の実績があり、交通事故対応スペシャリストの弁護士が在籍しております。
- 初回相談・着手金:無料
- 弁護士費用特約未加入者:完全成果報酬
- 弁護士費用特約加入者:実質0円(保険からのお支払いのため)
- 事前予約で休日・時間外の無料相談OK:LINEから無料相談
簡単な相談からでも大丈夫ですので、ちょっとでもなにかしらの不安を抱えている方はぜひ一度ご相談くださいませ。