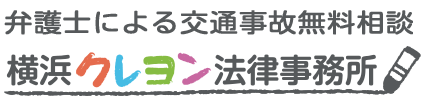著者情報
弁護士 鈴木 晶
一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
交通事故に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。

交通事故被害者に逸失利益が認められるには、その方に収入があることや、交通事故によって労働能力を喪失・低下してしまったことなどが求められます。逸失利益の請求ができるかどうかで全体の賠償額が大きく変わってきますので、これが認められるかどうかは被害者の方にとって重大な関心事といえるでしょう。
当記事で「逸失利益が認められるのはどんなケースなのか」、逆に「どんなケースで認められないのか」について説明していますので、参考にしていただければと思います。
逸失利益の概要

交通事故により「後遺症でこれまでと同じ業務をこなせなくなった」などの問題が起こり得ます。そんなときは逸失利益を加算した損害賠償請求を行いましょう。事故がきっかけで実際に支出した治療費、心身への苦痛などを理由とする慰謝料などに加え、将来の減収分を想定した逸失利益を請求することで受け取ることができる金額も大きく変わってきます。
“得られるはずであった収入が得られなくなった”ということを根拠としていますので、請求をするにはただ怪我をしただけでなく、①事故で後遺症を負った、②事故で死亡した、という被害の発生が必要です。
※このときの後遺症は「後遺障害」として認定される必要がある。
なお、「治療期間中に働くことができず収入が減った」「病院への通院が原因で勤務時間が短縮され、収入が減った」といった実害は損害賠償請求のうち「休業損害」として請求を行いますので逸失利益とは異なります。休業損害については、その損失が現に発生していれば後遺症や死亡という結果がなくても請求が可能です。
収入・労働能力・年齢がポイント
後遺障害の認定や死亡という結果があっても、絶対的に逸失利益の請求が認められるわけではありません。「労働することで得られる将来の収入が減ったのか」が重要ですので、次の3点が逸失利益の有無および請求金額におけるポイントといえるでしょう。
- 収入
(現在の収入が大きいほど、将来にわたり得られる収入も大きいと考えられる。逸失利益について考えるときは「基礎収入」と呼ばれる。) - 労働能力
(交通事故によって低下した労働能力の程度が大きいほど、逸失利益も大きいと考えられる。) - 年齢
(年齢が若いほど労働能力低下による影響が大きいと考えられる。)
逸失利益の額を計算する方法も1つではありませんが、原則として採用されるのはライプニッツ係数を用いる次の算式です。基礎収入が大きいほど、労働能力の低下具合が大きいほど、年齢が若いほど、請求額は大きくなるようにできています。
逸失利益 = ①基礎収入×②労働能力喪失率×③ライプニッツ係数
※ライプニッツ係数は労働能力喪失期間に対応して具体的な値が定まる。
ポイント①基礎収入の有無

逸失利益が認められるには、基礎収入が必要です。そのため会社員や個人事業主、会社経営者など、収入を得ていたことが示せる方ならこれまでの収入を提示して逸失利益を認めてもらうことはできるでしょう。
では収入を得ていない方はどうなるのでしょうか。実は、今現在において収入を得ていることは必須とはされておらず、無職の方でも学生の方でも、主夫・主婦の方などにも逸失利益が認められるケースはあります。
| 無職 | 現在無職でも「今後も就労する蓋然性がない」と評価をされなければ、逸失利益が認められるケースはある。例えば就職活動に取り組んでいれば否定される可能性は下がる。 |
| 学生や未就学児 | 将来的に働いて収入が発生する蓋然性が高く、逸失利益は認められやすい。 |
| 主夫・主婦 | 専業で家事をしている方でも、家事労働には経済的な価値があると評価されることから逸失利益は認められやすい。 |
| 年金受給者 | 後遺障害により支給額は減額されないため、逸失利益は認められない。 一方で死亡したときは、将来受けるべきであった年金について逸失利益が認められる。 |
なお、家賃収入などの不労所得を得ている方に逸失利益は認められないと考えられています。逸失利益は労働による収入を根拠としていることから、労働の対価として得ているわけではない“不労”所得に関しては基礎収入に算入できないのです。
減収のないケースではどうか
将来減収するであろう収入分を見越して逸失利益は発生します。では減収が起こらなかったケースではどうなるのでしょうか。例えば公務員など特定の職種では、収入に対する保障がなされており後遺障害を負っても将来に渡り減収されない可能性が高いです。
このときの逸失利益については次の2つの考え方があります。
- 差額説
「事故がなければ得られたはずの収入」と「事故後現実に得られた収入」の差額を損害と捉える。この場合、減収がないなら逸失利益が認められない。 - 労働能力喪失説
「労働能力の喪失」それ自体を損害と捉える。減収の有無は労働能力低下の程度を評価する一資料として用いるに過ぎず、減収がなくても逸失利益は認められることがある。
過去の裁判では、減収がないなら逸失利益を認めないとする差額説を採用した例もあります。しかし多くの裁判例では労働能力喪失説を採用し、減収がなくても認める傾向にあります。
ただしその場合であっても次のような事情が考慮されますので、労働能力喪失の有無だけで逸失利益が確約されるわけではありません。
- 収入の維持について本人が努力をしているか
- 収入の維持が勤務先の配慮や温情によるものか
- 昇進や昇給における不利益が生じる可能性の有無
- 業務への支障があるか
- 退職や転職が必要となる可能性の有無 など
ポイント②労働能力の喪失

逸失利益が認められるためのポイント2つ目が「労働能力喪失の有無」です。
交通事故で死亡という結果が生じたときは喪失率が100%ということになりますし、後遺障害を負ったときは後遺障害の程度に応じて喪失率が決まります。
※後遺障害の程度は“後遺障害等級”により判定する。
では労働能力との関係性が微妙な後遺症が残ったときはどうなるのでしょうか。その場面における労働能力は、被害者の職種などを鑑みて個別に評価します。
| 外貌醜状 | 顔や首など露出した部分に大きな傷跡、あざなどが残ったときの後遺障害が「外貌醜状」。 身体的な機能は低下しないため労働能力への影響が認められないことも多いが、モデルなどの人前に出る仕事や営業マンなど、悪影響が及ぶケースもある。このときは逸失利益が認められる可能性が高くなる。 |
| 歯の後遺障害 | 歯を欠損するなど、歯牙障害を負っても、労働能力に影響しないことが多い。 ただしスポーツ選手や力仕事をしている方など、歯を強く食いしばる必要のある仕事であれば歯の後遺障害を理由に認められる可能性が高くなる。 |
| 味覚や嗅覚の後遺障害 | 顔面や脳への損傷がきっかけで味覚障害・嗅覚障害を負うこともあるが、多くの職種では労働能力に影響しない。 他方で、調理を行う仕事や食品を取り扱う特定の仕事など、味覚・嗅覚を仕事で使っている場合は認められる可能性が高くなる。 |
| 下肢の短縮障害 | 骨折がきっかけで脚が少し短くなってしまうこともあるが、その短縮がごくわずかであれば仕事への影響がほぼ出ない。 しかしとび職やスポーツ選手など、影響が大きな職種であれば認められる可能性が高くなる。 |
被害者が障害者のケースではどうか
逸失利益が認められるには労働能力の喪失が必要であるところ、被害者の方が障害者であって、労働が元より難しいケースもあります。
昔には障害者に対して逸失利益が認められなかった裁判例もありますが(慰謝料として考慮されることはある)、近年では個々の障害の重さを考慮し、今後どのような収入が得られるのかを細かく評価する傾向にあります。
ただしその金額については争いが起こることも珍しくなく、また、適当な評価をすることも簡単ではありません。もし一般企業への就職可能性が低いと思われる程度に重度の障害であれば、平均労働者並みの金額は認められにくいでしょう。他方で、障害者であっても健常者の平均給与を基準に算定し、健常者と同等の金額が認められるケースはあります。
ポイント③労働能力喪失期間の有無

労働能力喪失期間も、逸失利益を認めるうえで重要なポイントといえます。
仮に労働能力の喪失が認められるとしても、その方がすでに高齢で定年退職しているのであれば逸失利益が認められないケースもあります。一般的には「18歳~67歳までの期間」で算定されますので、若い年齢であるほど金額は大きくなり、他方で被害者の方がすでに68歳以上であるときは認められにくいです。
とはいえ交通事故が起こるまで働いていたのであれば所得を得ていますし、その金額を基準に逸失利益は認められます。その場合は平均余命を用いて、現在の年齢からの期間で金額を計算します。
逸失利益を認めてくれないときの対応

仕事をしており、事故によって労働能力が低下しているときでも、加害者側が逸失利益について認めてくれないこともあります。
多くの場合は事故発生後、車を運転していた方が加入する保険会社との交渉(示談)が始まるのですが、そのとき「その後遺障害の内容では逸失利益は認められません」などと言われてしまうことも起こり得ます。示談交渉の段階では逸失利益をどのように判定するか当事者に委ねられていますので、相手方は逸失利益相当分を支払わないと主張することも自由なのです。
逆に、逸失利益がないとする主張を受け入れないことも自由ですので、保険会社の言い分をそのまま認めてしまわないことが大事です。
相手方が受け入れるかどうかではなく「最終的に訴訟を提起したとすれば、逸失利益は認められるのだろうか」という視点から評価しましょう。当初保険会社が逸失利益を認めていなくても、裁判によって逸失利益が認められる・逸失利益が増額されるケースはあります。
もし「保険会社の言い分が正当なのかわからない」「保険会社と交渉が上手くできるかわからない」と少しでも不安がある方は弁護士にご相談ください。
横浜クレヨン法律事務所では年間150件以上の交通事故案件を取り扱い、年間相談件数は400件以上の実績があり、交通事故対応スペシャリストの弁護士が在籍しております。
- 初回相談・着手金:無料
- 弁護士費用特約未加入者:完全成果報酬
- 弁護士費用特約加入者:実質0円(保険からのお支払いのため)
- 事前予約で休日・時間外の無料相談OK:LINEから無料相談
簡単な相談からでも大丈夫ですので、ちょっとでもなにかしらの不安を抱えている方はぜひ一度ご相談くださいませ。